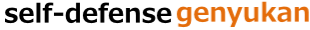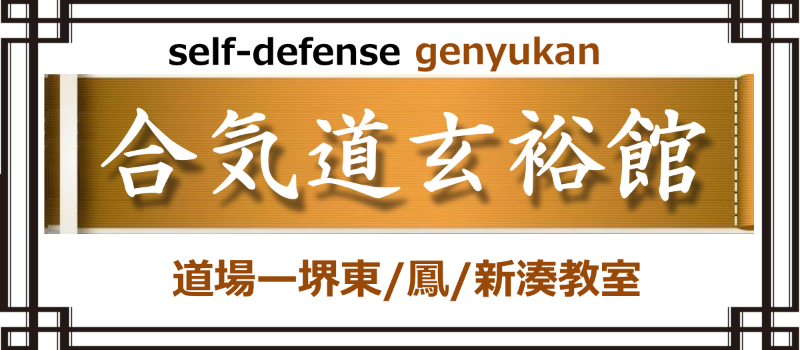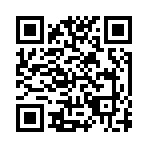稽古内容|合気道・堺市玄裕館
子供クラス

合気道玄裕館の指導員は皆自分の仕事を持ち良識ある社会人で構成していますので安心して子供さんを預けてください。
核家族化,少子化,地域における地縁的なつながりの 希薄化により、子供たちの人とのつながりが不足していると言われています。
道場において一般の社会人とつながりをもつことで、社会に適応できるコミニュケーション能力が身につくことと思います。
そして、武道、礼儀の指導だけでなく、武道を通じて「人間」を教えることにも重視しています。
家庭のしつけや学校の指導だけでなく、子供さんが道を踏み外すことのないようにしっかりと見守り続ける第三者機関的役割も果たしています。
初心者の人は、受け身や腕を捕まれたら外す稽古からはじめます。厳しくそして楽しく、子供の成長にあわせた指導をしています。
また、定期的に進級試験を行っていますので段階的に上達を目指すことができます。
一般クラス

「武道はやってみたいけど自分にはちょっと・・・」という武道の敷居が高いと感じている方へ
当会の特徴は体育会系のノリではなく、どちらかと言うと文系・理系の雰囲気で行ってます。それは、技の術理を科学的に指導しているためです。
武道には縁がないと思っている方は、必ず上達できるカリュキュラムで指導いたしておりますので、ご安心して参加ください。
当会では、今まで運動した事のない方、50才を過ぎてから武道を始めた方も多く在籍しています。
また、最近では、主婦の方、親子で参加される方も増えてきいる傾向です。
合気道・護身術の技
まずは、受け方から練習します。突きや蹴りに対して、上段を受けたり、外から受けたり、内から受けたり、下段を受けたりと・・・初心者の方はまずは止まっての稽古。上級になるにつれ徐々に動きをつけ、相手をさばいたりします。
空手のような一撃必殺ではなく「仮当」で投げや関節技を仕掛ける隙をつくります。しかし、仮当てでなく、急所への攻撃法もあり、一撃必殺の技法も含んでいます。(危険なので本気で当てたりはしませんのでご安心を)
投げられての受身も当然ですが、危険から逃れるために自ら受身をとります。とくに、腕を極められたときに逃れるのに有効です。
腕を掴まれたときや、後ろから抱きつかれたとき等、慌てることなく、知恵の輪のような感覚でほどいていきます。
コツをつかめば、あっという間に力もかけずに相手と逆転していることもよくあります。
合気道玄裕館のメインともいってもいいでしょう。相手の腕を制することが一番の方法です。離脱法の連続技として関節技に移行します。
上級になれば、突きに対してとか、瞬時に技をかけたりします。「何がおこった?」かわからないかも知れません。
これも、ゆっくりとしたペースから行っていきますので、次第に上手になっていますので、ご安心ください。
柔道のような一本をとる投げ技ではなく、こちらも離脱法の一種で、自分が不利な体勢から一転して相手を投げてしまうことで、逃れる方法です。
力が弱いとか体が小さいとか全然関係ありません。ちょっとしたコツと稽古が必要になってきます。
少し上達してきたら、相手が武器を持った状態での稽古を行います。型から入るので、普段の稽古をきちんとしていれば、大丈夫です。
腕や足に、ちょっとした押さえ方をすると激痛がはしります。こちらも、安全に行いますので、何ら心配はいりません。痛いのに何故か笑いがおきてしまいます。
合気道なのに締め技?玄裕館は合気道だけでなく合気道を通じ日本古来の柔術も研究しております。
型から学ぶものはたくさんあります。技そのものももちろんですが、体の使い方、重心移動、集中力、礼儀作法等です。ひとつの型をとっても大変奥深いものがあります。
稽古例
稽古例1
 |
 |
後ろからかなり強く腕を握られてますが、体の方向を少し変えるだけで、右写真のように相手の腕を制することができます。ほとんど力はいりません。
シンプルな動きでなので覚えやすく何度も繰り返し練習し技を覚えることができます。
稽古例2
 |
 |
腕を捕まれ引っ張られているところを右写真のようにコロンと倒します。こちらもシンプルな動きですので、繰り返し稽古を行うことで技が身に付きます。